6歳差育児って、「上の子が手伝ってくれるから楽そう」と思われがちですが、実際は、年が離れているからこその悩みがたくさんあります。
私も上の子(女の子14歳)、下の子(男の子8歳)の6歳差姉弟を育てながら、何度も「どうしたらいいの…」と悩みました。
- 上の子の心のケア
- 下の子のこだわり対応
- 学校行事が重なって大変
- 外出時の荷物が多すぎる
- 習い事の送迎調整
でも、今だからこそ思います。
6歳差育児には大変なことも多いけれど、その分、素晴らしい瞬間やメリットもたくさんあるんです。
この記事では、私が6歳差育児で実際にぶつかった悩みと、その乗り越え方を正直にお伝えします。
同じように悩んでいるママの心が、少しでも軽くなりますように。
6歳差育児で実際に困ったこと

年齢が離れているからこそ起こる特有の問題がいくつもありました。
上の子の心の変化
弟が生まれた時、上の子はまだ5歳。しかも誕生日が2日違いで、上の子の誕生日当日は私がまだ入院中でした。
後日、退院してから改めてお祝いしましたが、やっぱり少し寂しかったかもしれません。
弟の誕生を喜びながらも、注目が弟に集まることで複雑な気持ちを抱えていたと思います。
6歳差だと、つい「もうお姉ちゃんでしょ」と言ってしまいがち。でも、まだまだ甘えたい年頃。
私も上の子に頼りすぎて、寂しい思いをさせてしまったなと今では反省しています。
下の子特有のこだわりとわがまま
下の子が1歳くらいの頃、季節の変わり目は本当に大変でした。
半袖から長袖に変えるだけで大泣き、長袖から半袖に戻す時も同様。
毎回ひと苦労でした。
足のサイズが変わって新しい靴を買っても、「前のがいい!」と泣いて大騒ぎ。
今では「新しい靴ほしい」と言うようになり、成長を感じます。
「これがいい!」と決めたら泣いてでも主張するタイプ。
上の子が譲ってくれることも多く、つい下の子中心になってしまうこともありました。
そんな時は「今日はお姉ちゃん優先!」とバランスを取るようにしていました。
外出時の大変さ
これは6歳差育児あるあるかもしれません。上の子でようやく荷物が減ったと思ったら、今度は下の子の分でまた増える…。
飲み物をこぼしたり、服を汚したりすることも多いので、着替えはいつも必須アイテムでした。(実は、今でも下の子の着替えを車に常備しています(笑))
小さい頃はベビーカーもあったので、両手が使えるリュックが欠かせませんでした。
片手でベビーカーを押しながら、もう片方の手で上の子と手をつなぐことも多く、肩掛けバッグは不便に感じたのを覚えています。
荷物が多い時期だからこそ、使いやすいバッグ選びが本当に大事だなと実感しました。
6歳差育児ならではのメリット
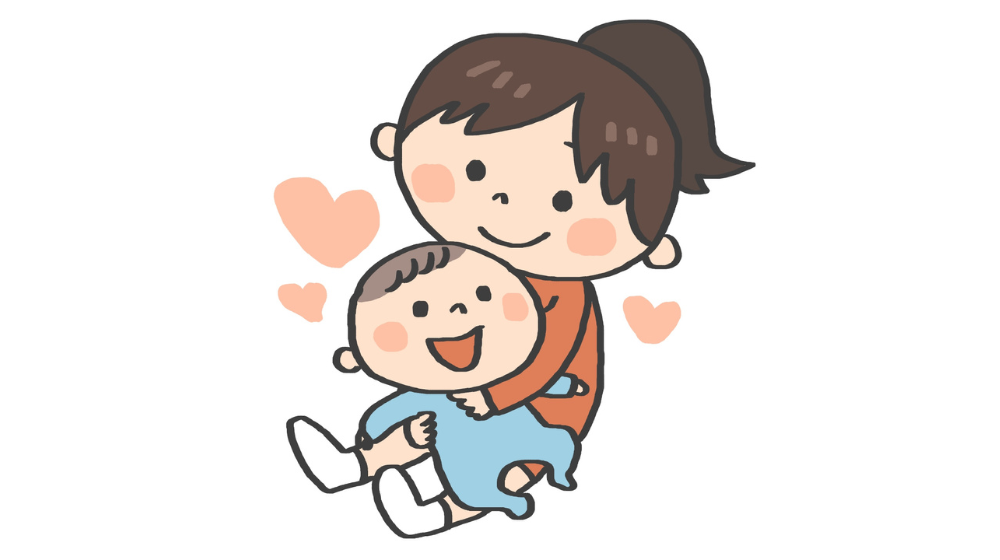
大変なことばかりお話しましたが、6歳差育児には良い面もたくさんあります。
年が離れているからこそ助けられたこと、家族の絆が深まったことも多かったです。
上の子が頼もしい存在に
私の地域では、学童のお迎えは中学生以上からOK。
部活が休みの日に下の子を迎えに行ってくれたこともあり、私が忙しい時や体調を崩した時は本当に助かりました。
弟と一緒にYouTubeを見たり、ゲームをしたり。
弟の友達が遊びに来ても、一緒に遊んでくれる優しいお姉ちゃんです。
6歳差があることで、ケンカが少なく、自然と面倒を見てくれるようになりました。
家族の協力体制ができる
下の子が赤ちゃんの頃、夜泣きが本当にひどくて大変でした。
日中は上の子の世話もあり、私はクタクタ…。
でも夜更かしタイプのパパが、夜泣き対応を担当してくれたおかげで、少しでも休むことができました。
下の子が生まれて間もない頃、上の子がインフルエンザに。
パパと一緒に寝てもらい、少し隔離したおかげで誰にも移らず済みました。
年が離れているからこそできる対策でした。
(ちなみにパパはこれまで一度もインフルエンザにかかった事がありません😲(笑))
学校行事やイベントでの対応

6歳差だと、学校行事のタイミングが重なることもあれば、まったく違う時期になることもあります。
それぞれの成長段階が違うからこそ、スケジュール調整はなかなか大変です。
行事が重なった時の対処法
中学校の参観日って、学年が上がるにつれて、だんだん行く親も少なくなるものですよね。
それでも、私はどうしても一番最初の参観日だけは見に行きたいと思っていました。
ところが、下の子の参観日と重なってしまいました。
下の子も1年生の最初の参観日で、「絶対に見に来てね!」とお願いされていたので、まずは下の子の学校へ。
参観が終わると、下の子を連れて上の子の中学校へ向かいました。
10分ほど様子を見ることができました。
上の子の成長した姿を少しでも見られて、なんだかホッとした気持ちになりました。
習い事の送迎調整
上の子は外部の陸上クラブ、下の子はドッジボールチームに所属しています。
特にドッジは3年生まで親の付き添いが必要で、送迎が重なると本当に大変です。
そんな日は、私が上の子を送ってから下の子の練習へ行き、迎えはパパが担当。
家族みんなで分担しながら、ようやく予定を回しています。
6歳差育児は、家族全員で協力しないと回らないと実感する日々です。
それぞれの時間を大切に
小学校も別々、運動会も別日。
上の子の陸上大会やバレエ発表会では、下の子も長時間同行。
逆に下の子のドッジボール大会では、応援や付き添いで親がつきっきり。
スケジュール調整は本当に大変ですが、どちらの頑張る姿も見られるのは親としての喜びでもあります。
上の子だけの時間、下の子だけの時間、それぞれにかけがえのない思い出が生まれています。
6歳差育児ママの1日のスケジュール(わが家のリアル)
上の子は中学生の女の子、下の子は小学生の男の子。
登校時間も帰宅時間も違い、さらに夕方はそれぞれの習い事でバタバタ!
ここでは、平日と習い事がある日の2パターンを紹介します。
パターン①:平日の基本スケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 6:00 | ママ起床・夫のお弁当作り&朝食準備 |
| 6:30 | 上の子(中学生)起床・朝食・登校準備 |
| 6:50 | 下の子(小学生)起床・朝食・身支度 |
| 7:20 | 下の子登校 |
| 7:35 | 上の子登校(髪の準備などで少し遅め) |
| 8:00 | ママ片付け・洗濯など家事タイム |
| 10:00〜14:00 | 在宅ワークやブログ作業。昼食は簡単に |
| 14:30 | 下の子帰宅→おやつ・宿題 |
| 18:00 | 夕食(家族そろってゆっくり) |
| 19:00〜21:00 | 家事や翌日の準備。上の子は勉強、下の子はテレビや自由時間 |
| 21:30 | 下の子就寝/上の子は自由時間 |
| 22:00 | 上の子就寝・ママのリラックスタイム |
パターン②:習い事がある日のスケジュール
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 6:00〜7:35 | 朝の流れは平日と同じ |
| 14:30 | 下の子帰宅→おやつ・宿題 |
| 17:00 | 上の子帰宅(部活あり)・軽めの夕食 |
| 18:15 | 上の子を陸上クラブへ送迎 |
| 19:00〜21:00 | 下の子ドッジボール練習(曜日による) |
| 21:00 | 上の子帰宅・ドッジが終わる時間なので、3人でお風呂タイム |
| 21:30 | 上の子宿題/下の子就寝 |
| 22:30 | 上の子就寝・ママの自由時間(ドラマや推し活など) |
夜は上の子の部活や下の子のドッジが終わる時間がちょうど重なるので、
21時頃に3人でお風呂に入って1日をリセットするのがわが家の定番です。
夕方以降バタバタする事が多いですが、在宅で仕事が出来ているからこそ、このスケジュールをこなせているなと実感しています。
6歳差育児を乗り切る解決法とコツ

実際に6歳差育児を経験して学んだ、乗り切るためのコツをお伝えします。
家族の協力体制を作る
これが一番大事なことです。
家族の助けが絶対に必要です。
パパとの役割分担を明確にして、お互いの得意分野で協力し合うことが大切。
我が家では夜泣き対応、送迎、感染症対策など、さまざまな場面でパパに助けてもらいました。
上の子の接し方を見直す
6歳差があると、つい上の子を「もう大きい」と思ってしまいがちですが、実際はまだまだ子ども。甘えたい気持ちも、認めてもらいたい気持ちも強いんです。
【上の子の心のケアで意識したこと】
- 「もうお姉ちゃんでしょ」と言わないようにする
- 下の子だけでなく、上の子も甘えさせる時間を作る
- 「お姉ちゃん優先デー」を設ける
- 頼りすぎず、まだ子どもとして接する
「もうお姉ちゃんだから」と思いすぎていたなと感じます。
でも、少しずつ関わり方を見直すうちに、上の子の表情がふっとやわらかくなっていきました。
実用的な準備とアイテム
- 収納力のあるカバン(荷物が多いため)
- 着替え一式(下の子がこぼすことが多いため)
- ベビーカー(小さい頃は必須)
行事やイベントが重なることも多いため、スケジュールは余裕を持って組むことが大切です。
「無理をしない」意識を持つだけでも、気持ちがラクになります。
下の子のこだわり対応
衣替えや靴の買い替えなど、下の子が嫌がることもありますが、焦らず見守るようにしていました。
時には上の子に我慢をしてもらうこともありますが、「今日はお姉ちゃん優先デー」のように、上の子の気持ちを大切にする日を作ってバランスを取りました。
今だから分かる6歳差育児の良さ

現在、上の子14歳、下の子が8歳になって分かることがあります。
少し手が離れた今だからこそ感じる、6歳差育児の“良さ”があります。
弟の存在があることで、上の子は責任感が強く、思いやりのある子に育ちました。
弟の面倒を見たり、一緒に遊んだりする中で、自然とリーダーシップも身についています。
お姉ちゃんをお手本にして育っているため、下の子は何事にも前向きで、覚えるのも早いです。
良い刺激を受けながら、楽しそうに成長している姿を見ると「6歳差でよかったな」と感じます。
年は離れていても、姉弟の仲はとても良好です。
それぞれの成長段階での関わり方ができるのも、6歳差ならではの魅力。
お互いを思いやりながら支え合う姿に、家族の絆の深さを感じます。
同じ6歳差育児で悩むママへのメッセージ

6歳差育児を経験してきた私から、同じように悩んでいるママたちに伝えたいことがあります。
年の近いきょうだいでも、離れたきょうだいでも、子どもを育てることは本当に大変。
離れているからこそ助かることもあれば、離れているからこそ苦労することもあります。
それが、6歳差育児の現実です。
一人で抱え込まずに、家族みんなで協力して乗り切ることが大切です。
ママ一人で頑張りすぎず、パパにも積極的に参加してもらうことを意識してみてください。
小さなことでも「助けてもらう」ことで、気持ちがぐっと楽になります。
6歳差だと、一緒にできないことも多いものです。
でもその分、それぞれ子どもとゆっくり向き合う時間を持てるのが魅力。
上の子だけの時間、下の子だけの時間、どちらもかけがえのない思い出になります。
衣替えを嫌がった下の子も、今では「新しい服欲しい」と言うようになりました。
その時は大変だと思っても、必ず変化する時が来ます。
今の大変さに振り回されすぎず、長い目で見てあげることが何より大切です。
まとめ
6歳差育児は確かに大変なこともたくさんあります。
上の子の心のケア、下の子のこだわり対応、外出時の荷物の多さ、行事の調整など──。
年が離れているからこその悩みがあるのも事実です。
でも、6歳差だからこその“良さ”もたくさんあります。
上の子の頼もしさ、家族の協力体制、それぞれの子どもとの特別な時間など、年の差があるからこそ得られる喜びもあるのです。
- 6歳差育児には特有の大変さがある
- 家族の協力が何より大切
- 上の子を「大きいから」と思わず、まだ子どもとして接する
- 外出時の準備とアイテムを工夫する
- 完璧を求めず、長い目で見る
同じ6歳差育児で悩んでいるママたちへ。
大変なことも多いけれど、きっとそれ以上に素晴らしい家族の思い出になります。
一人で抱え込まず、家族みんなで乗り切っていきましょう。
年の近いきょうだいでも、離れたきょうだいでも、それぞれに良さがあります。
6歳差ならではの“特別な家族の形”を、一緒に作っていきませんか?
6歳差育児でよくある質問
- Q6歳差育児は大変ですか?
- A
正直に言うと、大変なこともたくさんあります。
上の子の手がかからなくなったと思ったら、今度は下の子でまた育児スタート。
終わらない小学校生活…12年間!(笑)でも、年が離れているからこその良さもたくさんあります。
上の子が下の子の面倒を見てくれたり、それぞれとじっくり向き合う時間を持てたり。大変さもあるけれど、その分、喜びや発見も多いのが6歳差育児です。
- Q上の子に我慢させすぎていないか心配です
- A
私も同じように悩んだことがあります。
得に上の子が小学校に入学した頃。
環境の変化で不安もあったと思うのに、下の子はまだ1歳で手がかかる時期でした。上の子の大切な時期を、ちゃんと見てあげられていなかったなと反省しています。
下の子が保育園に通うようになってからは、「お姉ちゃん優先デー」を作るようにしました。
今でも、上の子だけと出かける時間を大切にしています。
- Q学校行事が重なったらどうしていますか?
- A
できる限り、どちらにも顔を出すようにしています。
本当は、どちらの行事もじっくり見てあげたいんです。
でも、どうしても重なってしまうときは、パパと手分けしたり、短時間でも様子を見に行くようにしています。完璧にはできなくても、「どちらも大切に思っているよ」という気持ちだけは伝えるようにしています。


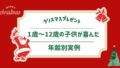
コメント